宮原(みやばる)神社~盛武姓の由来がここに


宮原神社=北川町長井字宮原4487=地元では、「ととみやさん」と呼んでいますが、由来は不明です。御祭神は「水波女命(みずはのめのみこと)」と「佐伯惟治霊(さえきこれはるのみたま)」。本殿は、千鳥破風(ちどりはふ)造りで広さは約1坪、拝殿は、切妻造りで14・1坪。千鳥破風とは、三角状にせり上がった屋根の装飾の一種。創建は不詳とされていますが、「宮崎県史蹟調査」によると、安永8亥(いのしし)年(1779)12月8日に延岡城主・内藤能登守政脩(まさのぶ)=延岡藩の第3代藩主。内藤家宗家8代=により社殿が再建され、寛政2年(1790)12月3日には延岡城主・備後守代祠官だった井本対馬守・藤原實久により鳥居が再建されており、歴代城主が厚く崇拝する社だったことが伺えます(宮崎神道青年会「宮巡」より)。明治4年11月に長井神社に合祀されましたが、同15年に再復鎮座されました。本社の御祭神「佐伯(大神)惟治」は豊後佐伯の城主でしたが、大友氏に追われ三川内の尾高智(おたかち)山で自害したと伝えられています。享年33歳。惟治の墓所は、北浦町大字三川内橋ケ谷の山腹にあります。入口鳥居に向かって右横に「佐伯惟治家臣供養塔」と「長袖様碑」。「長袖者」(ちょうしゅうしゃ)とは、「長い袖の衣服を着る身分や階級の高い人」のことで、碑文には「公家、医師、神職、僧職、学者などが豊後の国宇目郷・酒利(さかり)村を所領としていた盛獄(もりたけ)氏の末裔がこの地に移り住み、『盛武』の名を名乗ったといわれ、盛武氏の祖と云われている」と記されています。「宮原治水事業記念碑」は、明治3年に建立。用水工事は、旧延岡藩・滝口常裕を筆頭に着工し、約70ヘクタールの水田を潤したと伝えられています。完成を記念して「罔象女命(みつはのめのかみ)」(日本における代表的な水の神)を祀り、水防や豊穣を祈願しました。罔象女命は、アニメ映画「君の名は。」の主役、「宮水三葉」の「みつは」の由来になったと言われています。例祭日は12月13日。



















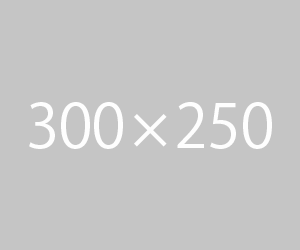
この記事へのコメントはありません。