八咫(やた)の烏碑~八戸村の由来

 北川散策⑤
北川散策⑤八戸は、日向と豊後の国境の村で、日向最後の口屋番所があった所。国道326号八戸トンネル出入り口には、「八戸村」のレリーフが刻まれ、「八」の文字は、は2羽のカラスが向かい合った形で表現され、その右下に「八咫烏」(やたがらす)の文字が刻まれています。八咫烏は日本神話に出ている三本足のカラス。熊野権現の神使と言われ、一飛びで七谷七峰を越える霊力を持つとされ、トンネルの西側入り口のすぐ下の旧国道脇には、「八戸烏」(やとがらす)を刻んだ石塔と、石塔の説明を書いた木柱が立っており、木柱には「烏をモチーフにしたこの碑は、元禄8年(1695)に建立されています。ここ八戸は、日向・豊後を結ぶ国境の宿場。梓山国境越えは行旅の難所、熊野権現の使いで、道案内の神とされる八咫の烏の信仰があったことがうかがえる」と記されています。「八咫」が「八戸」に転化したのでしょうか。八咫烏は、熊野で神武天皇の道案内を行い大和の国の平定を手助けしたことから、「勝利の導き手、勝利のシンボル」とされています。八咫とは、親指と中指を広げた長さを指し、八咫烏は、「大きいカラス」という意味。三本足は、「天」「地」「人」を表すとも言われます。その『八咫烏』を昭和6年(1931)、日本サッカー協会がシンボルとしました。旗の黄色は公正を、青色は青春を表わし、はつらつとした青春の意気に包まれた日本サッカー協会の公正の心構えを表現しているということです。ユ二ォームのエンブレムとして採用したのは、1987年からです。
















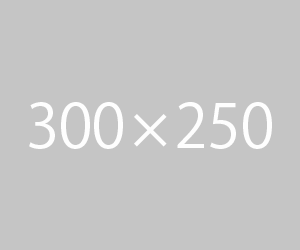
この記事へのコメントはありません。