馬鎮(まじめ)神社~牛馬神として崇敬

馬鎮神社=北川町川内名字市ヶ迫6159-ロ=創立年月日は不詳。明治4年11月に熊田の村社・川内名(かわちみょう)神社に合祀されましたが、同15年3月に復興鎮座しています。昭和3年(1928)2月10日、拝殿改造と上屋と廊下の増築、平成13年(2001)に拝殿を改造しました。本殿は、流破風(はふ)造り1坪、拝殿は、入母屋(いりもや)造り8坪。入母屋とは、日本建築の代表的な屋根の形で、上部が切妻造り、下部が寄棟造り。御祭神の「保食神」(うけもちのかみ)は、日本書紀では「食物を司る神」として描かれ、古事記ではイザナギ神、イザナミ神の神産みから生まれ、神名のオオゲツヒメとは「大いなる食物の女神」という意味。記紀ではスサノオとツキキヨミに切られ、その屍(しかばね)から、稲や稗、麦、大豆など様々な穀物や、蚕や栗、牛馬が生み出され、これらが種となり民が生きていく食物となったと伝えられています。「命を失うことで、食物が生まれる」という農耕観は、古代の穀物神信仰の原型とされています。 「馬鎮神社」は、馬の神様を祀る神社として古くから農業や交通の守護神として崇められてきました。馬に関する神々を祀る神社であり、特に馬の健康や安全を願うために建立されました。古代日本では、馬は交通手段や農耕の重要なパートナーとして広く使用されており、その神聖視は当たり前のこと。古代の祭祀や民間信仰に由来し、多くの地域に同様の神社が存在します。これらの神社は、特に農業を営む人々にとって、作物の成長や豊作を祈願する重要な場所として機能してきました。同じ名前の、馬鎮神社は、隣の佐伯市青山にもあり、享禄3年(1530) に創立されましたが、元和元年(1613) の洪水により社殿が流され、伏木川の住人汐月嘉右衛門が黒沢川との合流地点で御神体を発見し、これを捧持し、今の伏木川の地に奉祀し、社殿を建立したとされています。領内の牛馬神として崇敬され、遠くは大分県大野郡(現豊後大野市)や日向国(宮崎県)からも参詣の人々が訪れたと言われています。
















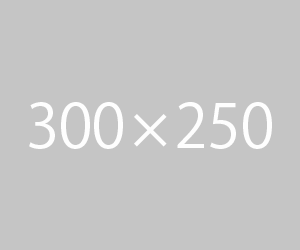
この記事へのコメントはありません。